|
|
| 抵当権抹消 |
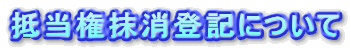
お金を借りたりして、不動産に担保権(抵当権や根抵当権)がある場合に、借金やローンを返済すれば、担保権の登記を抹消することになります。
抵当権抹消登記は、借入金完済後、できるだけ速やかに行った方が良いでしょう。
抵当権権抹消登記をせずに放置をしておくと
①不動産の売却、新たな抵当権設定がむずかしくなる
②金融機関等から入手した抹消登記申請書類の紛失・有効期限経過の危険がある
③さらに長期間(20年以上)放置すると、休眠担保権の抹消手続をすることになり余計な費用がかかる等が予想されます(下記ご参照ください。)。
抵当権が消滅する原因には以下のように、一般的な原因である①②と特殊な原因である③以下があります。
①債務(借金)の返済
②債権者と債務者による合意解除
③抵当不動産(土地、建物)の滅失
④第三者の目的不動産の時効取得
⑤抵当権の絶対的放棄
⑥混同(債権債務の混同と物権の混同があります)
⑦被担保債権の消滅時効(10年)
⑧抵当権の実行による競売
⑨代価弁済
⑩抵当権消滅請求
⑪休眠担保権の抹消(不動産登記法上認められています)
(根)抵当権者(金融機関など)
1.(根)抵当権の権利証(登記済証、登記識別情報)
2.登記原因証明情報(抵当権解除証書・放棄証書・弁済証書など)
3.会社法人等番号
4.本人確認情報(運転免許証・保険証など)
5.委任状(認印で可)
(根)抵当権設定者(不動産の所有者)
1.本人確認情報(運転免許証・保険証など)
2.委任状(認印で可)
休眠担保権とは、現在でも抹消されることなく残存する明治、大正、昭和初期に設定された古い担保権のことを言います。このような古い抵当権でも登記上抹消されずに残っている以上、その不動産は売却も新たな担保権設定もできません。
抵当権を抹消するには、抵当権者の協力が必要となりますが(上記必要書類の準備等)、休眠担保権の場合、なにぶん古い担保権ですので、担保権者が法人であれ個人であれ、そのまま存在していることはほとんどないでしょう。
このため、休眠担保権を抹消するためのいくつかの特別な方法が規定されています。
1.担保権者が行方不明でない場合(原則共同申請)
①担保権者または相続人全員・承継法人と協力し抹消手続きを行う
②担保権者である法人が、解散または清算結了の場合、清算人と協力し抹消手続きを行う。
③担保権者を訴える訴訟
2.担保権者が行方不明の場合(単独申請)
①「弁済証書」等による抹消(不動産登記法第70条第3項前段)
②「除権判決」による抹消(不動産登記法第70条第1項、第2項)
③弁済供託による抹消(不動産登記法第70条第3項後段)
④公示送達により担保権者を訴える訴訟
上記いずれの場合も、通常の抵当権抹消に比べ、調査・手続きに時間を要し、費用(裁判費用、供託費用、必要書類取得費用、司法書士報酬等)もかかります。
●通常の抵当権抹消の場合
| 報酬額 |
11,000円~ (※1) |
| 登録免許税 |
不動産1個につき 1,000円 |
| 実費等 |
登記事項証明書等の取寄費用 |
(※1)次の場合、報酬額はそれぞれ1100円加算。①不動産5個以上は1個ごと
●休眠担保権抹消の場合
| 報酬額 |
33,000円~ (※2) |
| 登録免許税 |
不動産1個につき 1,000円 |
| 実費等 |
裁判費用、供託費用、必要書類の取寄費用等 |
(※2)次の場合、報酬額はそれぞれ1100円加算。①不動産5個以上は1個ごと

お問い合せ先へ
関連ページ 抵当権設定へ
トップページへ
|
Copyright (c) 2008 齋藤司法書士事務所
|
|


