|
|
| 相続登記 |
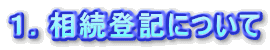
相続登記とは、亡くなられた方の不動産を相続人名義に登記をすることを言います。
相続登記は、相続の開始後、できるだけ速やかに行った方が良いでしょう。
相続登記をせずに放置をしておくと
①不動産の売却、抵当権設定に不便
②遺産分割協議が整ったとしても、他の相続人の気が変わって、共有名義に登記されてしまう危険がある
③第2、第3の相続が開始したため、権利関係が複雑になる
等が予想されます。
1.法定相続を行う場合
相続人全員が、法定相続分に従って相続する場合
2.遺産分割を行う場合
相続人のうち、1人または数人だけが相続するとか、法定相続に従わないで相続するときに相続人間で遺産の分配を協議することです。
法定相続人全員で遺産分割協議書を作成し、実印で署名押印する必要があります。
3.遺言による相続を行う場合
遺言者の指定した人が相続人になります。
遺言は、「1.法定相続」に優先します。
1.亡くなった方の,14、5歳から死亡時までの全戸籍謄本(除籍・改製原戸籍)
2.亡くなった方の、戸籍の附票(現存分のみで可)
3.相続対象不動産を特定するもの(名寄帳、登記済証など)
4.相続対象不動産の登記簿謄本・登記事項証明書
5.相続人全員の戸籍謄本・戸籍の附票 各1通
6.遺産分割の場合、遺産分割協議書(実印で押印)
7.遺産分割の場合、相続人全員の印鑑証明書
8.相続をする方の住民票の写し
9.遺言があるときは、遺言書
10.固定資産評価証明書
11.本人確認情報(運転免許書・保険証など、依頼者分)
12.委任状(認印で可)
※上記1、2、4、5、8、10は司法書士が取寄可能、6は司法書士が文案作成可能です
| 報酬額(登記申請) |
33,000円~ (※1) |
| 登録免許税 |
土地・建物の価額 × 0.4% |
| 必要書類の作成 |
5,500円~ |
| 実費等 |
戸籍謄本等、必要書類の取寄費用 |
(※1)次の場合、報酬額はそれぞれ1100円加算。①不動産の価額2000万円以上は500万円ごと、②不動産5個以上は1個ごと、③権利者4名以上は1名ごと

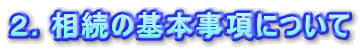
第1順位 配偶者2分の1、子2分の1
◎子が複数いる場合の相続分は、均等
◎子が相続開始時に亡くなっていた場合、代襲相続、再代襲相続等が発生します
◎胎児も相続人となります
◎非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分の2分の1。ただし、平成25年9月5日以降に開始した相続については同等
第2順位 配偶者3分の2、直系尊属(親)3分の1
◎直系尊属が複数いる場合の相続分は、均等
◎直系尊属間では、親等の近い方が優先します
第3順位 配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
◎兄弟姉妹が複数いる場合の相続分は、均等
◎兄弟姉妹が相続開始時に亡くなっていた場合、代襲相続が発生します
◎片親のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、全兄弟姉妹の相続分の2分の1
1.被相続人の遺言がある場合は、その遺言が上記の法定相続に優先します。
2.相続を承認した場合、積極財産だけでなく消極財産も相続します。
3.法定相続人であっても相続権を失う場合・・相続欠格者、廃除者。(ただし、代襲相続あり)
4.その他の制度
遺産分割協議、相続放棄、限定承認、遺留分減殺、特別受益者
寄与分、相続分の譲渡、相続分の取戻など
5.昭和56年1月1日以前に開始した法定相続は、現民法改正前のため上記とは異なります。
※用語
被相続人:亡くなった方
代襲相続:相続人の直系卑属(子)が、その相続人に代わって相続すること


相続に関連して以下の場合には、家庭裁判所へ申立てをする必要があります。
当事務所では、依頼者の代理人となることはできませんが、家庭裁判所への提出書類を作成いたします。
1.相続を放棄する場合 「相続放棄申述事件」(審判)
2.相続を限定承認する場合 「相続の限定承認申述事件」(審判)
3.相続開始後に遺言を発見した場合(公正証書遺言を除く) 「遺言書の検認申立事件」(審判)
4.遺言で指定された遺言執行者がいない場合 「遺言執行者の選任申立事件」(審判)
5.相続人間で遺産分割協議が調わない場合 「遺産分割調停申立事件」(調停)
6.親権者と未成年の子との間で遺産分割協議をする場合 「特別代理人選任申立事件」(審判)
7.遺産分割協議をする相続人が判断能力を欠く場合 「成年後見開始申立事件」(審判)
8.相続人が行方不明など、その所在・生死が明らかでない場合
「失踪宣告申立事件」(審判)
「不在者財産管理人選任申立事件」(審判)
9.相続人の存在・不存在が明らかでない場合 「相続財産管理人選任申立事件」(審判)
10.相続人不存在のとき特別縁故者が財産分与を申し出る場合
「特別縁故者に対する相続財産分与申立事件」(審判)
11.遺留分減殺請求を行使した遺留分権利者が相続財産の返還を求める場合
「遺留分減殺請求申立事件」(調停)
| 報酬額(書類作成) |
22,000円~ |
|
複雑・高度なもの 55,000円~ |
| 裁判手続費用 |
手数料・郵券など(およそ数千円) |
| 実費等 |
戸籍謄本等、必要書類の取寄費用 |


法定相続情報証明制度とは、平成29年5月から始まった制度で、法務局に法定相続情報一覧図(相続関係説明図)を備え、その写しの交付を受ければ、銀行預金、不動産、自動車、有価証券などの相続の手続きに戸籍謄本等の原本提出に代えることのできる制度です。
金融口座が多数ある方、複数の地方に不動産をお持ちの方などは、本手続を利用するとメリットが大きいと考えられます。
当事務所では、法定相続情報一覧図の作成、法務局への保管及び交付を取り扱っております。不動産の相続登記と同時に、または、不動産の相続登記がなくてもお引き受けいたします。お気軽にご用命ください。
1.利用できる方・・相続人
2.写しの再交付の申出期間・・最初の申出後5年間
3.管轄法務局・・①被相続人の本籍地、②被相続人の最後の住所地、③申出人の住所地、④被相続人名義の不動産所在地
4.一覧図には、全相続人の氏名、続柄、生年月日、現住所が記載されます
5.あくまで法定相続人の状態を証明するもので、遺産分割、相続放棄などの結果は反映されません
6.後日、相続人に新たな相続が発生した場合(2次相続)も反映されません。この場合、一通ではなく被相続人ごとに書面を揃える必要があります
| 報酬額(登記申請と併せて) |
相続登記費用合計+11,000円 |
| 報酬額(単独のご依頼) |
22,000円(相続人5人まで) |
|
33,000円(相続人6人以上) |
| 実費等 |
戸籍謄本等、必要書類の取寄費用 |

お問い合せ先へ
関連ページ 遺言へ
関連ページ 遺産承継へ
トップページへ
|
Copyright (c) 2008 齋藤司法書士事務所
|
|


