|
|
| 他不動産登記 |
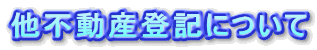
このページでは、
●建物の保存登記
●登記名義人住所・氏名の変更
●特殊な原因による所有権移転
●仮登記
●担保権の登記
●買戻権の登記
●用役権の登記
の概要について記載してあります。詳細は、当事務所まで、お気軽にお問い合わせください。
下記項目については、それぞれのページをご参照ください。
●相続
●売買・贈与
●抵当権設定
●抵当権抹消
家を新築した場合や建物が未登記の場合、この家が自分のものであることを証明するため、保存登記をします。また、保存登記の前に、表示の登記が必要ですが、これは、土地家屋調査士さんが申請します。
保存登記のための必要書類(基本的なもの)
1.住民票の写し 1通
2.住宅用家屋証明書(登録免許税軽減用)
3.表示登記の関係書類
4.本人確認情報(運転免許書・保険証など)
5.委任状(認印で可)
※住宅用家屋証明書は司法書士が取寄可能です。
費用の目安(税込み)
| 報酬額 |
22,000円~ (※1) |
| 登録免許税 |
不動産の価額 × 0.4% (下記以外) |
|
租税特別措置法の軽減措置 |
|
・住宅用家屋 不動産の価額 × 0.15% |
|
・優良住宅等 不動産の価額 × 0.10% |
| 実費等 |
登記事項証明書、必要書類などの取寄費用 |
(※1)次の場合、報酬額はそれぞれ1100円加算。①不動産の価額2000万円以上は500万円ごと、②権利者4名以上は1名ごと
(※2)表示の登記には、費用が別途必要です。
所有者の住所・氏名が、登記記録に記載されているものと現在の住所・氏名が異なる場合、変更登記をする必要があります。市役所、町村役場で住民票や戸籍の変更をしても、登記記録が自動的に変更されるわけではないからです。
住所や氏名に変更があった場合、なるべく早く変更登記申請をすることをお勧めします。
変更登記の必要書類(基本的なもの)
1.住民票の写し、戸籍の附票 1通 (住所変更の場合)
2.戸籍謄本 1通 (氏名変更の場合)
3.本人確認情報(運転免許書・保険証など)
4.委任状(認印で可)
費用の目安(税込み)
| 報酬額 |
11,000円~ (※1) |
| 登録免許税 |
不動産1個につき 1,000円 |
| 実費等 |
登記事項証明書、必要書類などのの取寄費用 |
(※1)次の場合、報酬額はそれぞれ1100円加算。①不動産5個以上は1個ごと
不動産の所有権移転(名義書換)をするには、その原因を特定しなければなりません。
代表的な原因は、売買、贈与、相続ですが、以下のとおり特殊なものがあります。
法律行為によるもの
(1)時効取得
(2)民法第958条の3の審判・・・特別縁故者への移転
(3)特別縁故者不存在確定
(4)遺留分減殺
取引行為によるもの
(1)代物弁済・・・債務者所有の不動産を代物弁済する契約をした場合、担保仮登記に基づく本登記
(2)交換
(3)譲渡担保・・・譲渡担保契約が成立した場合
(4)債務弁済・・・譲渡担保につき債務弁済した場合
(5)財産分与・・・離婚にともなう財産分与の協議が成立した場合
(6)現物出資
(7)持分放棄・・・共有者の一人が持分を放棄した場合
(8)共有物分割・・・共有不動産の現物分割
(9)遺産分割・・・共同相続の登記をした後の遺産分割
(10)合意解除・・・売買による移転登記をした後の売買契約の合意解除
(11)委任の終了・・・権利能力なき社団の代表者の交代の場合
その他
(1)真正な登記名義の回復
費用の目安(税込み)
| 報酬額 |
33,000円~ (※1) |
| 登録免許税 |
不動産の価額 × 2% |
| 実費等 |
登記事項証明書、必要書類などのの取寄費用 |
(※1)次の場合、報酬額はそれぞれ1100円加算。①不動産の価額2000万円以上は500万円ごと、②不動産5個以上は1個ごと、③権利者4名以上は1名ごと
(注)登記済証・登記識別情報がない方で、法務局提出の本人確認情報が必要な場合は、別途費用がかかります。
登記申請の書類が不足していたり、売買予約など将来物権変動が見込まれる場合など、一定の条件を満たせば仮登記を申請することができます。
仮登記はあくまでも仮の登記ですので、第三者に対する対抗力はありませんが、登記順位を確保する効力があります。
なお、当事務所では、虚偽の仮登記を防止するため、ご本人様確認・意志確認を厳格におこなっておりますので、ご協力おねがいいたします。
仮登記の種類
(1)条件不備の仮登記
・登記済証、登記識別情報を添付できないとき
・取引が成立したにもかかわらず登記義務者が登記申請に協力しないとき
(2)請求権保全の仮登記
・売買予約
・保証人の将来求償権をあらかじめ担保する抵当権設定予約
(3)始期付・条件付権利の仮登記
・死因贈与契約
・農地法所定の許可前の農地の売買契約
・売買代金完済時に所有権が移転する旨の特約がある売買契約
・仮登記担保法に基づく、代物弁済の予約、代物弁済契約
仮登記のための必要書類
1.印鑑証明書(発行から3か月以内のもの) 1通
2.登記原因証明情報(契約書など)
3.登記義務者の承諾書(権利者単独申請の場合)
4.固定資産評価証明書
5.本人確認情報(運転免許書・保険証など)
6.委任状(実印または認印で押印)
所有権移転仮登記の費用の目安(税込み)
| 報酬額 |
移転登記の報酬額の70% (※1) |
| 登録免許税 |
不動産の価額 × 1% |
| 実費等 |
登記事項証明書、必要書類などのの取寄費用 |
(※1)次の場合、報酬額はそれぞれ770円加算。①不動産の価額2000万円以上は500万円ごと、②不動産5個以上は1個ごと、③権利者4名以上は1名ごと
(注)登記済証・登記識別情報がない方で、法務局提出の本人確認情報が必要な場合は、別途費用がかかります。
登記をすることができる担保権として、抵当権(根抵当権を含む)、質権、先取特権があります。
また、特殊な形態の担保権として、譲渡担保、仮登記担保権、工場抵当があります。
当事務所では、各種担保権に関する登記手続きを取り扱っておりますので、詳細等など、お気軽にお問い合わせください。
1.抵当権の登記について
下記抵当権の登記手続きがあります。
(1)抵当権設定
(2)抵当権抹消
(3)追加担保
(4)債権譲渡、代位弁済による抵当権移転
(5)抵当権者の会社合併、相続等による抵当権移転
(6)債権額、利息、損害金、債務者住所・氏名変更による変更登記
(7)債務引受、相続等による債務者変更
(8)転抵当権の設定
(9)抵当権の譲渡・放棄・順位変更
2.根抵当権の登記について
根抵当権とは、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保する抵当権です。
抵当権が、1回の貸付けに対して不動産を担保とするのに対し、根抵当権は一定の期間内に継続的に発生する貸付けや売掛金等に対して不動産を担保とします。また、根抵当権は、その不動産から優先的に支払いを受けることのできる極度額もあわせて設定します。
根抵当権の3要素・・①債権の範囲、②極度額、③債務者
根抵当権には、下記の登記手続きがあります。
(1)根抵当権設定
(2)根抵当権抹消
(3)追加担保
(4)債権の範囲の変更
(5)極度額の変更
(6)債務者の変更
(7)元本確定期日の変更
(8)債務者の相続による指定債務者の合意
(9)根抵当権者の会社合併、相続等による根抵当権移転
(10)全部譲渡、一部譲渡、分割譲渡による根抵当権移転
(11)共有根抵当権の優先の定め
(12)元本確定
3.先取特権の登記について
先取特権とは、民法その他法律で定められた債権を有する者が、債務者の総財産及び特定の財産から、他の債権者に優先して弁済を受けることのできる、法定の担保物権です。
法定の担保物権ですので、抵当権のように当事者が設定契約をする必要はありません。
先取特権には、下記の登記手続きがあります。
(1)一般の先取特権保存
(2)不動産保存の先取特権保存
(3)不動産工事の先取特権保存
(4)不動産売買の先取特権保存
(5)各種先取特権の変更、移転、抹消
4.質権の登記について
不動産質権とは、債権者が、債務者からその債権の担保として、目的不動産の引渡しを受け、債務が弁済されるまで債権者がその不動産を占有することができる担保物権です。
このように、質権は不動産担保の提供者から担保物の占有を奪ってしまうため、実務上では、不動産に質権を設定することはほとんどありません。
不動産質権には、下記の登記手続きがあります。
(1)質権設定
(2)質権変更、移転、抹消
5.譲渡担保の登記について
譲渡担保とは、債務の担保として債務者(または第三者)所有の財産(不動産など)を債権者に移転することをいいます。
不動産を目的として、譲渡担保契約をした場合は、「譲渡担保」原因として、債務者から債権者へ「所有権移転」登記をおこないます。
また債務者が、債務を弁済し譲渡担保契約を解除した場合、「債務弁済」または「譲渡担保契約解除」を原因として、債権者から債務者へ「所有権移転」登記をおこないます。
6.仮登記担保の登記について
仮登記担保とは、債務の担保として、その債務の不履行がある場合には、債務者所有の不動産を債権者に移転することを目的として、「代物弁済予約契約」や「停止条件付代物弁済契約」をすることによって、目的の不動産に所有権移転の仮登記を設定することをいいます。
仮登記担保は、「仮登記担保法」という法律に規定されています。
仮登記担保には、下記の登記手続きがあります。
(1)代物弁済予約契約による所有権移転請求権仮登記
(2)停止条件付代物弁済契約による条件付所有権移転仮登記
(3)担保権実行による所有権移転の本登記
(4)受戻しによる担保仮登記の抹消
7.工場抵当の登記について
工場抵当とは、工場抵当法に基づき、工場に属する土地または建物に設定した抵当権の効力が、土地または建物に備え付けられた機械・器具等にも及ぶものとされる抵当権のことをいいます。
工場抵当の設定登記は、
(1)通常の抵当権設定登記+「機械器具目録」の添付
(2)工場財団の所有権保存登記+抵当権設定登記
があります。
8.費用の目安(税込み、5.譲渡担保、6.仮登記担保は除く)
| 報酬額 |
設定登記 |
22,000円~ |
| (※2) |
移転登記 |
22,000円~ |
|
変更登記 |
16,500円~ |
|
抹消登記 |
11,000円~ |
|
(休眠担保権抹消の場合、21,600円~) |
|
財団保存登記 |
55,000円~ |
|
財団目録の変更 |
22,000円~ |
|
|
|
| 登録免許税 |
設定登記 |
債権額 × 0.4%(下記以外) |
|
|
租税特別措置法の軽減措置 |
|
|
・住宅用家屋 債権額 × 0.1% |
|
|
追加設定の場合 追加不動産1個につき1,500円 |
|
移転登記 |
債権額 × 0.1%(相続、会社合併の場合) |
|
|
債権額 × 0.2%(相続、会社合併以外の場合) |
|
抹消登記 |
不動産1個につき 1,000円 |
|
財団保存登記 |
財団1個につき 30,000円 |
|
財団抵当権 |
債権額 × 2.5% |
|
|
|
| 実費等 |
|
登記事項証明書、必要書類などの取寄費用 |
(※1)5.譲渡担保、6.仮登記担保の費用は、所有権移転、及び仮登記に準じます。
(※2)次の場合、報酬額はそれぞれ1100円加算。①債権額2000万円以上は500万円ごと、②不動産5個以上は1個ごと、③権利者4名以上は1名ごと
買戻の特約とは、売買契約に際し、後日、不動産の売主が売買代金と契約費用を買主に返還して、不動産所有権を売主が買い戻すことができる権利で、民法第579条以下に規定されています。
実務上では、権利移転型の担保制度として利用されています。
登記された買戻権は、1個の物権たる性格を持ち、第三者に対抗することができます。
ただし、買戻権の登記は、売買による所有権移転の登記申請と同時に別個の申請によってしなければならず、後から買戻権だけの登記を申請することはできません。
下記買戻権の登記手続きがあります。
(1)買戻特約の登記
(2)買戻権移転
(3)買戻期間満了・混同による買戻権抹消
(4)買戻権行使による所有権移転
買戻特約登記の費用の目安(税込み)
| 報酬額 |
22,000円~ (※1) |
| 登録免許税 |
不動産1個につき 1,000円 |
| 実費等 |
登記事項証明書、必要書類などのの取寄費用 |
(※1)次の場合、報酬額はそれぞれ1100円加算。①売買価格2000万円以上は500万円ごと、②不動産5個以上は1個ごと、③権利者4名以上は1名ごと
用益権とは、簡単に言うと他人の不動産を使用する権利のことです。
現在、登記することができる用益権は賃借権、地上権、地役権、永小作権、採石権となっています。
(1)賃借権
・賃借権は、賃貸人が賃借人に土地または建物を使用収益させ、これに対して賃借人が賃料を支払うことを約すことにより成立します。
・賃貸人との特約がない限り、賃借人には登記請求権はありません。
(2)地上権
・地上権は、土地の工作物または竹木を所有するために他人の土地を利用する権利です。
・地上権設定契約による方法と法定地上権により取得する場合があります。
・土地の空間、地下の一定の範囲にも区分地上権を設定できます。
(3)地役権
・地役権は、あらかじめ定めた目的に従い、他人の土地(承益地)を自分の土地(要役地)の便益に供する権利です。
・主な地役権としては、通行地役権、電線路の設置等があります。
(4)永小作権
・永小作権は、耕作または牧畜を目的として、小作料を支払って他人の土地を利用する権利です。
(5)採石権
・採石権は、他人の土地において、岩石を採取する権利です。
費用の目安(税込み)
| 報酬額 |
設定登記 |
22,000円~ |
| (※1) |
移転登記 |
22,000円~ |
|
変更登記 |
16,500円~ |
|
抹消登記 |
11,000円~ |
| 登録免許税 |
設定登記 |
不動産の価額 × 1.0% (除く地役権) |
|
移転登記 |
不動産の価額 × 0.2%(相続、会社合併の場合) |
|
|
不動産の価額 × 1.0%(相続、会社合併以外の場合) |
|
抹消登記 |
不動産1個につき 1,000円 |
(※1)次の場合、報酬額はそれぞれ1100円加算。①不動産の価額2000万円以上は500万円ごと、②不動産5個以上は1個ごと、③権利者4名以上は1名ごと

お問い合せ先へ
トップページへ
|
Copyright (c) 2008 齋藤司法書士事務所
|
|


